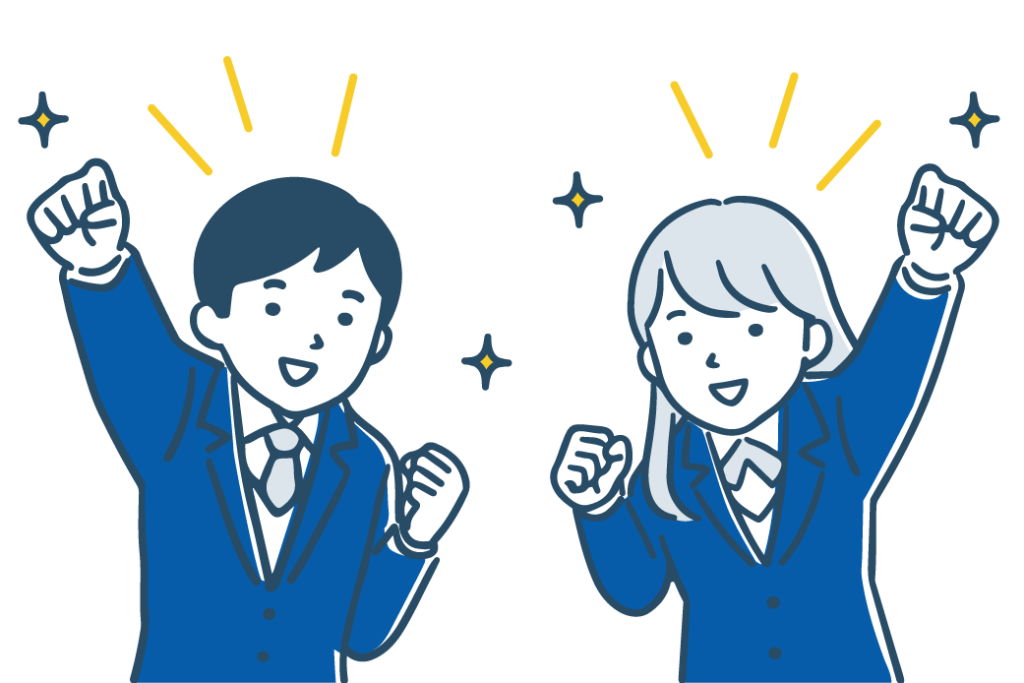私立大学入試の基本構造
①一般方式(個別入試)
特徴
-大学が独自に出題
-試験科目は大学・学部により異なる(例:英・国・選択1科目)
-マーク式/記述式/小論文/面接など多様
試験日程
-1月下旬〜2月中旬がピーク
-同じ大学でも日程・方式により複数回受験可能(「全学部日程」「個別日程」など)
配点例(例:英語重視型など)
-英語200点・国語100点・選択100点など、学部の特性によって変化
②共通テスト利用方式
特徴
-大学入学共通テストの得点のみで判定
-試験会場に行かずに出願・受験できる
-複数の学部・方式に同時出願できる
メリット
-共通テストの得点を複数大学・学部に流用できる
-スケジュール的にも私立個別試験と併願しやすい
③併用方式
出願の自由度と併願戦略
【出願可能数】制限なし(何校でも出願可)
【試験方式】同一大学・学部でも複数方式あり(戦略的併願が可能)
【試験科目】英・国中心が多い。数学や理科を選べる学部も
「得意科目を活かす出願」「複数方式併願で安全網を確保」などの戦略が可能。
合否判定のポイント
試験結果
大学独自試験・共通テストの得点
比重
英語重視型、総合型、1科目型など多彩|高得点科目だけ利用する方式もあり
その他
面接・小論文の有無は大学により異なる・書類審査不要が多い
私立大学入試の戦略ポイント
【複数出願が前提】同じ大学で複数回受験も可能。チャンスを増やせる
【得意科目重視】数学なし・英語1科目入試など多様な選択肢あり
【共通テスト活用】高得点が出れば、複数大学に同時出願できる武器に
【試験日程を管理】日程が重ならないようにカレンダーで併願調整を
国公立大学vs私立大学一般選抜比較表
| 比較項目 | 国公立大学 | 私立大学 |
| 試験方式 | 共通テスト+個別試験(二次試験) | 主に大学独自試験(共通テスト利用型あり) |
| 共通テストの活用 | 必須(ほぼすべての学部で利用) | 一部利用(方式により異なる) |
| 試験日程 | 全国共通:前期2月下旬/後期3月上旬 | 大学ごとに異なる(1月下旬〜2月下旬) |
| 学費(目安) | 約53万円/年(授業料) ※国立は全国一律 | 約80〜150万円/年 (学部により異なる) |
| 校数・選択肢の数 | 限られる(全国に約180校) | 非常に多い(全国に約600校) |
| 対策の特性 | 幅広い科目+記述力が必要 | 英語・国語・数学中心の対策が多い |
| 主な受験スタイル | 総合力重視・バランス型 | 得意科目勝負・方式選択がカギ |
補足ポイント
-国公立は「共通テスト+記述」のハードルが高いが、費用面や進路の幅に魅力あり
-私立は「複数出願・科目選択」で戦略的に合格を狙いやすいが、学費は高め
-併願戦略では「国公立+私立」を組み合わせるのが一般的
志望校選びは、合格の可能性を高めるだけでなく、大学進学後の満足度にも大きく関わる重要なプロセスです。
志望校選びの戦略ポイント
【目的軸】何のために進学するのかを明確にする
学びたい学問がある
学部のカリキュラム、教授陣、研究実績を見る
資格・就職に強い大学
就職実績、資格試験の合格率、キャリア支援
環境やライフスタイル重視
学費、通学距離、キャンパスの雰囲気
将来の進学(大学院など)も視野に
研究環境、進学実績、留学制度など
【成績軸】合格可能性のあるバランスを取る
挑戦校(チャレンジ)
合格可能性30〜40%程度
モチベーションの源に
実力相応校(実力型)
合格可能性50〜60%程度
安定した受験準備の中心軸
安全校(すべり止め)
合格可能性70%以上
最低1〜2校は確保
注意点
チャレンジ校に偏りすぎない!「受かる入試」と「通いたい学校」のバランスがカギ。
【方式軸】入試方式を戦略的に選ぶ
共通テスト+二次試験(国公立)
バランス重視。記述力と幅広い科目対策が必要
私立一般(独自試験)
得意科目を活かしやすい。複数出願が可能
共通テスト利用(私立)
共通テストの得点だけで出願可能。併願に最適
総合型・学校推薦型選抜
書類・面接・プレゼン重視。早期対策が必要
数の方式を組み合わせて「広く・深く」合格ルートを確保!
【情報軸】最新情報を定期的にチェック
大学の募集要項、配点、出題傾向、試験科目は毎年変わる場合も
オープンキャンパスや大学説明会には積極的に参加
先輩や塾の先生の声も貴重な参考に
【費用・生活軸】合格後の生活も見据える
学費
初年度納入金、奨学金制度
一人暮らし
家賃、生活費、仕送りの有無
通学
実家から通えるか、交通費はどれくらいか
志望校選びの合言葉は「夢・実力・現実」
-夢(行きたい)
-実力(受かる)
-現実(通える・払える)
この3つをしっかりバランスさせて、後悔のない進路選びを!